- 刺毒魚・・・主にヒレなどのトゲに毒を持っている魚です。
- 食中毒魚・・・内臓・筋肉・皮膚などに毒を持っている魚です。
刺毒魚とは
刺毒魚の場合は扱い方を間違えると皮膚を刺されて、毒によって痛んだりしびれるような症状がでます。
ヒレ、頭部やエラブタに有毒のトゲがあります。
魚を素手で触らないようにしましょう!
食用で持ち帰るときは事前にハサミでトゲの先端をカットして持ち帰るようにしましょう。
刺された場合、痛みは半日から一日つづきます。
応急処置は熱湯やカイロで温めると痛みが一時的に和らぎます。
痛みが長引くようなら、病院で適切な処置をするようにしてください。
アイゴ

ゴンズイ

ハオコゼ

堤防釣りで釣れます。
最大で22cmと小型の毒魚です。
夜釣り等見極めが難しい状況でカサゴと見誤り、安易に触って刺されるケースが多いです。
背びれに毒があります。
触るときはフィッシュグリップを必ず使うようにしましょう。
アカエイ

オニカサゴ

食中毒魚とは
- テドロキシン・・・フグ類
- シガテラ毒・・・イシガキダイ
- パリトキシン様毒・・・ソウシハギ
テドロキシンの代表魚はフグで、どんな種類でも処理免許がないとさばいてはいけないことになってます。
シガテラ毒は主に熱帯・亜熱帯地域でプランクトンが作り出す毒で、食物連鎖を通じてそれが大型魚の体内に蓄積します。
パトリキシン様毒の代表魚はソウシハギです。近年東京からも近い伊豆大島などでも目撃例が増えています。
キタマクラ

名前の由来は死人の枕を北にむけるというところから来ています。
カワハギに風貌が似ています。
持ち帰らないことが基本です。
クサフグ

さわっても害はないのですが、皮膚・内臓・筋肉に毒をもっています。
食用として食べようすると中毒を起こすことが知られています。
フグの資格者がさばいた筋肉の食用は厚労省で認められています。
咬毒生物 とは
海に棲む咬毒生物といえばウミヘビが有名ですが釣りで出会う可能性は極めて低いです。
釣れる可能性があって咬毒を持つ生物として代表的なのはヒョウモンダコです。
他にはマダコやサメハダテナガダコが毒を持っています。
- ウミヘビ
- ヒョウモンダコ
- マダコ
- サメハダテナガダコ
ヒョウモンダコ

毒魚に共通する注意事項
毒魚を靴で踏んで外す、海に蹴っ飛ばして逃がす場合は履物の底が薄いと毒トゲが貫通することもあるので十分注意が必要です。
刺されたり、咬まれたりすると毒がある魚は手では触らないことが重要です。
小魚タイプであればフィッシュグリップなどで掴んでからハリを外しリリースしてください。
大きな毒魚はハリス部分をハサミで切って逃がしてしまう方が良いでしょう。
楽しい釣行には予備知識は必要です。
安全に釣りを楽しみましょう。


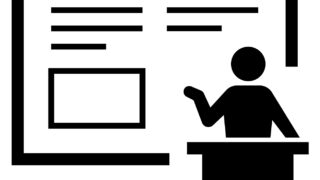
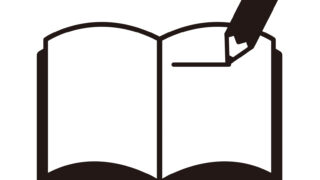
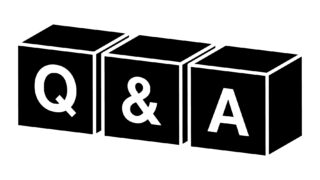


コメント